介護保険の施設、特別養護老人ホームや老人保健施設、あるいはショートスティの料金は、世帯の収入によって利用料金の負担限度額を軽減できる制度がある。
負担限度額認定制度というのだが。
これが、だんだん条件が厳しくなってきている。
負担限度額認定制度とは何か
特別養護老人ホームや老人保健施設、介護療養型医療施設に入所したりショートステイを利用すると、介護サービス費用の自己負担分(1割もしくは2割)+居住費や食費などを負担することになる。
とはいえ、お金や貯金のない人は住居費や食費をまともに支払うと、収入が追い付かない。
というわけで、所得の低く、預貯金も少ない人が、特別養護老人ホームや老人保健施設、介護療養型医療施設に入所したりショートステイを利用する場合は、その所得に応じ、居住費・食費の自己負担の上限額(負担限度額)が定められている。
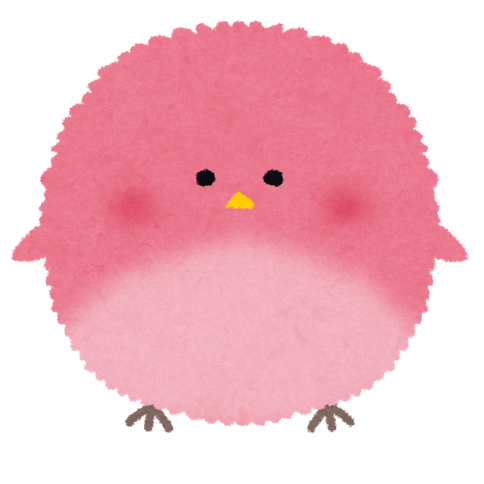
負担限度額認定制度はお金のない人も介護で困らないように、介護の自己負担額を通常より減らす制度なんですね。
介護保険の「負担限度額認定」の対象となる介護サービスとならないサービス
介護保険の負担限度額認定の対象となる介護サービスとならない介護サービスがあるので注意しよう。
介護保険の「負担限度額認定」の対象となる介護サービス
介護保険の「負担限度額認定」の対象となる介護サービスは
これらの介護サービスは「負担限度額認定」の対象となる。
介護保険の「負担限度額認定」の対象とならない介護サービス
以上の介護サービスは「負担限度額認定」の対象とならない。
だんだんと厳しくなる負担限度額認定制度
この「負担限度額認定制度」だが、徐々に条件が厳しくなっている。
平成3年(2021年)8月から負担限度額認定の対象となる預貯金の条件が変わった。
負担限度額認定の対象となる世帯収入の段階
負担限度額の対象となる世帯収入の段階は現在4段階。
本人の収入と世帯収入によって区分される。
第1段階の対象となる人
これは、変わりなし。
第2段階の対象となる人
ここも変わりなし。
第3段階の対象となる人
こちらは、第三段階が2つに分けられた。
介護保険の負担限度額認定制度の対象となる預貯金の条件
介護保険の負担限度額認定の対象となるかならないか、どのくらいの金額になるのかは世帯収入と預貯金の額が関係してくる。
平成3年(2021年)7月までの負担限度額認定制度の対象預貯金
の両方の条件が満たされることが必要というのが、平成3年(2021年)7月までの負担限度額認定制度の対象条件だった。
実際の負担限度額(負担の上限)は世帯収入によって4段階に区分されていた。
平成3年(2021年)8月からの負担限度額認定制度の対象預貯金
平成3年(2021年)8月からの負担限度額認定制度から、対象となる預貯金額が大幅に変わった。
かつ
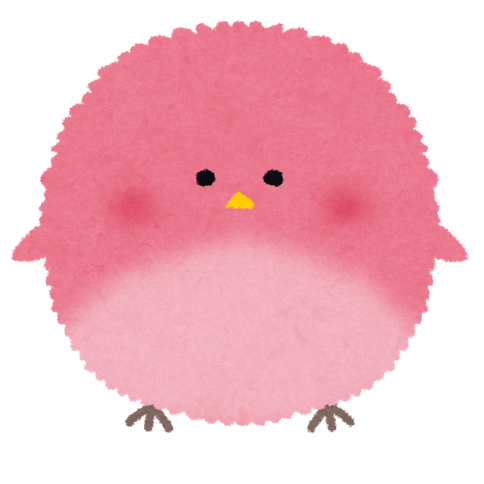
実は第4段階という収入段階もあるけど、特例はあるけど基本的には負担限度額認定制度の対象ではないのです。
以下の条件をすべて満たしている場合。
・属する世帯の構成員数が2人以上である
・介護保険料を滞納していない
・世帯における現金および預貯金などが450万円以下(債券や有価証券などを含む)
・家屋や日常生活に必要な資産を除き不要な資産を所有していない
・介護保険施設に入所または入院しており第4段階の食費や居住費を負担
・世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込み額を除いた額が80万円以下
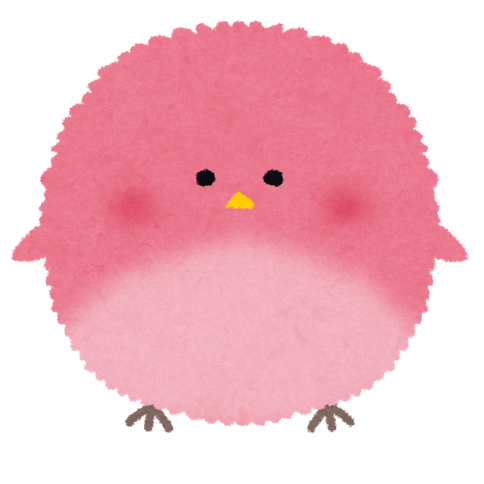
ずいぶん厳しくなったなあ。という印象ですね。
預貯金に含まれるもの
預貯金に含まれるのは
・株式・投資信託・債券
・金銀などの貴金属
・現金
平成3年(2021年)8月からの負担限度額(自己負担限度額)
では、実際の自己負担額の上限額(負担限度額)がいくらか?
上の図をご覧の通り、居住費の負担額が60円(日額)引き上った。
食費を含めると下の表のようになる。
介護費用を安くしようと思うなら
負担限度額認定制度で言うところの世帯は、本人、配偶者(世帯分離している配偶者、内縁関係者を含む)世帯員のこと。
子供の同居は不利になる
「あの家の息子(娘)は親と一緒に暮らしているんだって。なんて親孝行なんだろう」というのは、負担限度額認定制度を受けようと思うには不利になる。
安く介護サービスを使おうと思ったら、「子供と同居したい」と思っちゃダメ!
まあ、同居している子供が仕事をしていない、住民税非課税者なら問題ないけど。
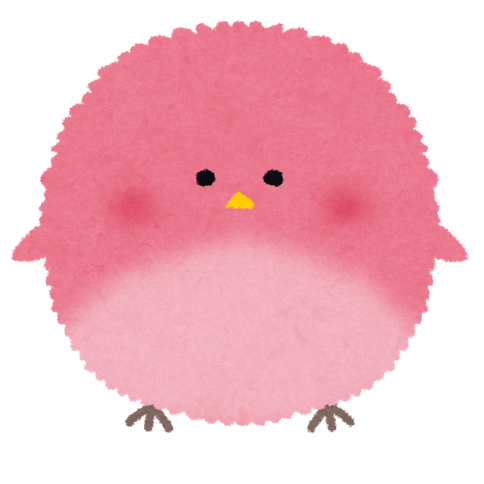
ちなみに、同じ家に住んでいても、戸籍上世帯が別(世帯分離という)。
という風にすることはできる。
ただし、万が一不正受給といわれても責任持てません…。
配偶者が別居してても意味がない
ところで、「特別養護老人ホームへ入れば、本人の住所は老人ホームになるので負担限度額は安くなる」と思うかもしれないが、配偶者に関しては世帯が違っても意味はない。
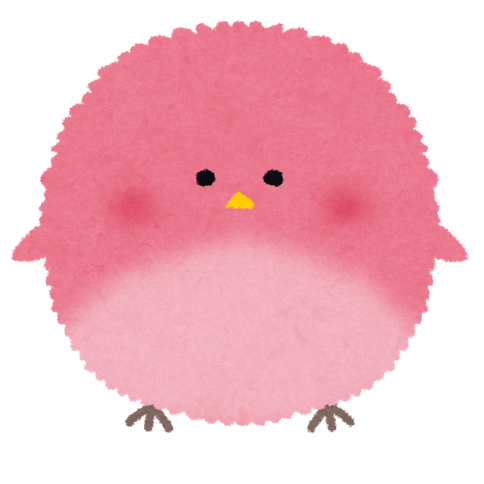
離婚しない限り、別居していても妻と夫の預金は「合算される」。
また、夫婦として戸籍に入っていない場合でも、実態があれば妻と夫の預金として「合算される」。
限度額負担認定の手続き
市役所窓口で以下のものを提出する。
本人が限度額負担認定申請する場合
市町村役場に以下のものを持参する。
・預貯金の写し(本人、配偶者/表紙、残高のわかるページ)
・同意書(これも役所でもらうことができる)
・本人、配偶者の印鑑
・本人確認のできるもの(免許証・マイナンバーカード等)
申請書に個人番号を記入するとちょっと面倒になるので、記入しなくてもいいかどうか、市町村窓口に聞いてみたほうがいいかも。
代理人が限度額負担認定申請する場合
- 被保険者本人の個人番号と確認用の書類
- 代理人の身元を保証するもの(免許証・マイナンバーカード等)
- 法定代理人の場合は戸籍謄本、任意代理人の場合は委任状
身分を証明する 書類等については各市町村窓口に問い合わせを必ずして、必要なものを用意する。






コメント