認知症や障害で判断能力が不十分な人の利益を守るためにあるのが成年後見制度。
本人の代わりに、財産管理や契約の手伝いをしてくれたりする。
では、成年後見制度を使うための申し立てはだれがする?
成年後見制度の申し立てができる人
成年後見制度は家庭裁判所に申し立てをして、後見人(保佐人・補助人)を選んでもらう。
その申し立てができるのは
1.本人
2.配偶者
3.4親等内の親族
4.市区町村長
5.検察官
6.成年後見人等,任意後見人,任意後見受任者,成年後見監督人等
市区町村長からの成年後見申し立て
市区町村長からの成年後見申し立ては
に行われる。
場合によって(虐待などの場合)は、配偶者・4親等内の親族がいても、成年後見の必要があるのに、配偶者・4親等内の親族に申し立てをする気が無い場合には市町村長が申立人になる場合がある。
ちなみに2親等内の親族とは、兄弟姉妹・祖父母・孫のことを言う。
もちろん、市長そのものが申し立てに動いたりするわけではなくて、市役所の職員が、市長の名のもとに動く。
ただし、市町村によっては、
「成年後見の類型が補佐・後見人になるだろう見込みがある場合しか市区町村長からの成年後見申し立てを行わない。」
というところもある。
で、どの類型になるか?という判断は、包括支援センターの職員がすることが多い。
類型が補助程度で、親族が申し立てをする気が無い場合は、包括支援センターが本人や親族を説得して「本人申し立て」「親族申し立て」に持ってゆく。
成年後見人(保佐人・補助人)・成年後見監督人からの成年後見申し立て
一度成年後見制度の申し立てをしたが、判断能力の低下がさらに進んだり、あるいは、判断能力が回復したりした場合、成年後見人(保佐人・補助人)・成年後見監督人からの成年後見申し立てがされることがある。
任意後見人・任意後見受任者からの成年後見制度の申し立て
判断能力の低下が進んできて、法的な成年後見制度を利用したほうが良いと任意後見人・任意後見受任者が判断した場合、家庭裁判所に成年後見制度の申し立てをする場合がある。
検察官からの成年後見申し立て
検察官からの成年後見申し立てはほとんど行われない。
本人からの成年後見申し立て
成年後見制度の申し立てには「本人が申し立てる」というのもある。
大体の場合、本人は判断能力が低くなっているので、成年後見制度の必要性を感じない。
なので、本人申し立ての場合、包括支援センターの職員などが本人を説得したり、成年後見制度申し立ての手伝いをする。
成年後見制度申し立ての手伝いといっても、まあ、ほぼ手続き全て、ケアマネなどと協力しながら包括支援センターの職員が行う。
市町村などによっては、専門の係が市役所にある場合もあるのかもしれないが…。
親族からの成年後見申し立て
親族からも成年後見制度利用の申し立てができる。
手続きができる親族なら、自分たちで手続きする。
が、難しければ、包括支援センター等の職員が手伝う。
というか、これまた、手続きのほとんどを包括支援センター等の職員が行う状況になる。

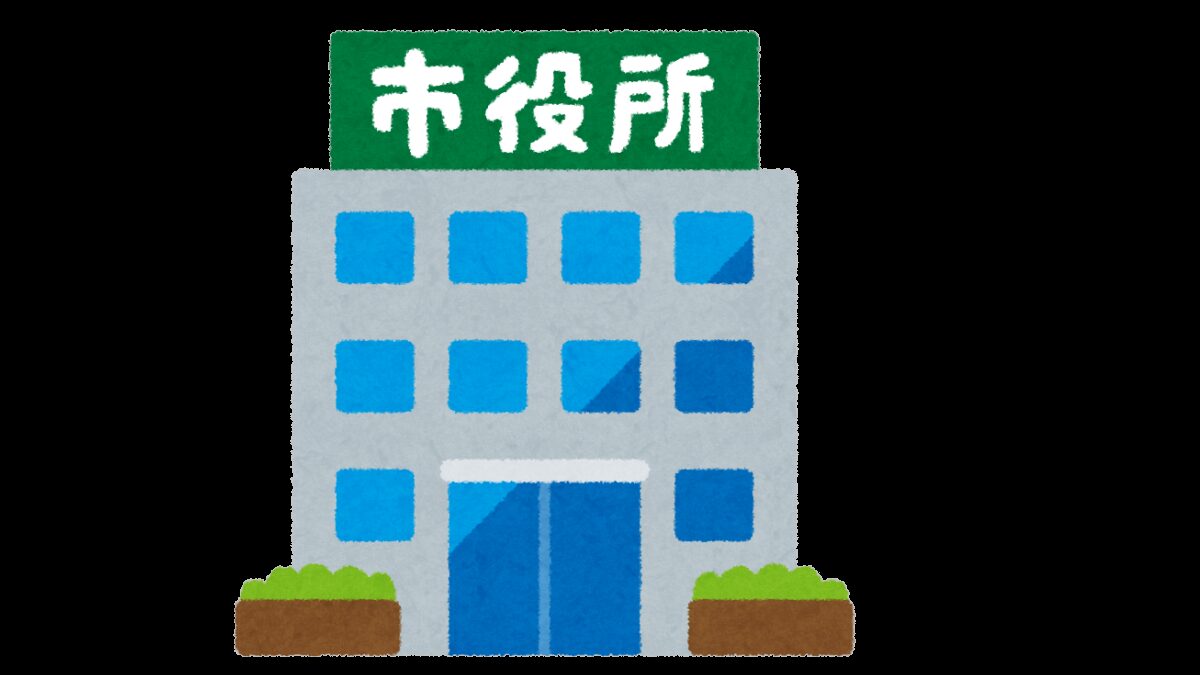


コメント