65歳未満の医療費は3割負担。
結構高いという感覚があると思う。
少しでも、医療費を安くするための方法が無いのだろうか?
ちょっとだけ医療費の自己負担を安くする方法は実はある。
それはどんな方法?
医療費の自己負担が安くなるのは少しづつでも、重なるとそれなりの金額になる。
マイナンバーカードを保険証にする
マイナンバーカードを保険証にする。
いわゆる、マイナ保険証で医療機関を受診すると、90%位の医療機関で少しだけ医療費の自己負担が安くなる。
まあ、マイナ保険証の利用促進のための施策だ。
マイナ保険証を利用し診療情報の提供に同意した場合に、従来の健康保険証よりも医療費の自己負担が安くなるようにしている。
まあ、せいぜい1回の受診で数円の違いだけど。
いくつも医療機関にかかっていたり、年に何回も医療機関を受診すると、塵も積もれば山となるで、それなりに医療費の自己負担金額に差が出る。
薬局へは「お薬手帳」持参する
「お薬手帳」を薬局に持参して、医療機関で処方された薬をもらうと、薬の代金に含まれる「服薬管理指導料」というのが安くなる。
「服薬管理指導料」は、薬剤師が患者に安全に薬を使用してもらうために必要な情報の収集・分析・管理・記録や、薬を渡す時の説明に対して与えられる報酬(点数)のこと。
2. 1.以外の場合 ・・・・・・59点
3. 介護老人福祉施設等を訪問して行なった場合(月4回まで。ショート利用期間中も対象) ・・・・・45点
薬はジェネリック医薬品を選ぶ
薬そのものの値段を安く抑えたければ、ジェネリック医薬品を選ぶ。
高価な薬でもジェネリック医薬品はだいぶ安いので、お得感が大きい。
薬をもらうなら院内薬局が一番安い
薬局の立地や規模によって、同じ薬が処方されても自己負担額が違ってくる。
これは、「調剤基本料」というものが違うため。
基本的には、院内薬局が一番安くて、次がチェーン店、門前薬局(病院の前にある薬局となり、個人経営の薬局が一番高上り。
月をまたいだ入院はできるだけ避ける
緊急入院とかはどうしようもないが、できるだけ入院は月をまたがない方が医療費の自己負担が安く済む。
これは高額療養費制度という、医療費が一定金額以上になった時に、一定額以上の医療費を払わなくて済む制度。
高額療養費制度は、1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻される。
基本的に、後で払い戻しを受けるか、市町村で限度額適用認定証を発行してもらい、医療機関で初めから限度額しか払わなくて良いようにするかだが、オンライン資格確認システムを導入している医療機関や薬局の窓口で、限度額適用認定証情報の利用に口頭または画面操作で「同意」すれば、「限度額適用認定証」の準備は不要。
また、マイナ保険証の利用でも「限度額適用認定証」の準備はいらない。
基準が1日から月末なので、入院日数は同じでも、月をまたぐと自己負担が増えることになる。
医療費を確定申告する
「ほんの少ししか還付金が戻ってこないので医療費の確定申告はしない」という人が多いが、もし、医療費の自己負担額が少しでも基準をオーバーするようなら医療費の確定申告はした方が良い。
所得税の還付金はほんのわずかでも、住民税に影響が出る。
また、「家族全員の医療費を所得の多い人が確定申告する」が基本。
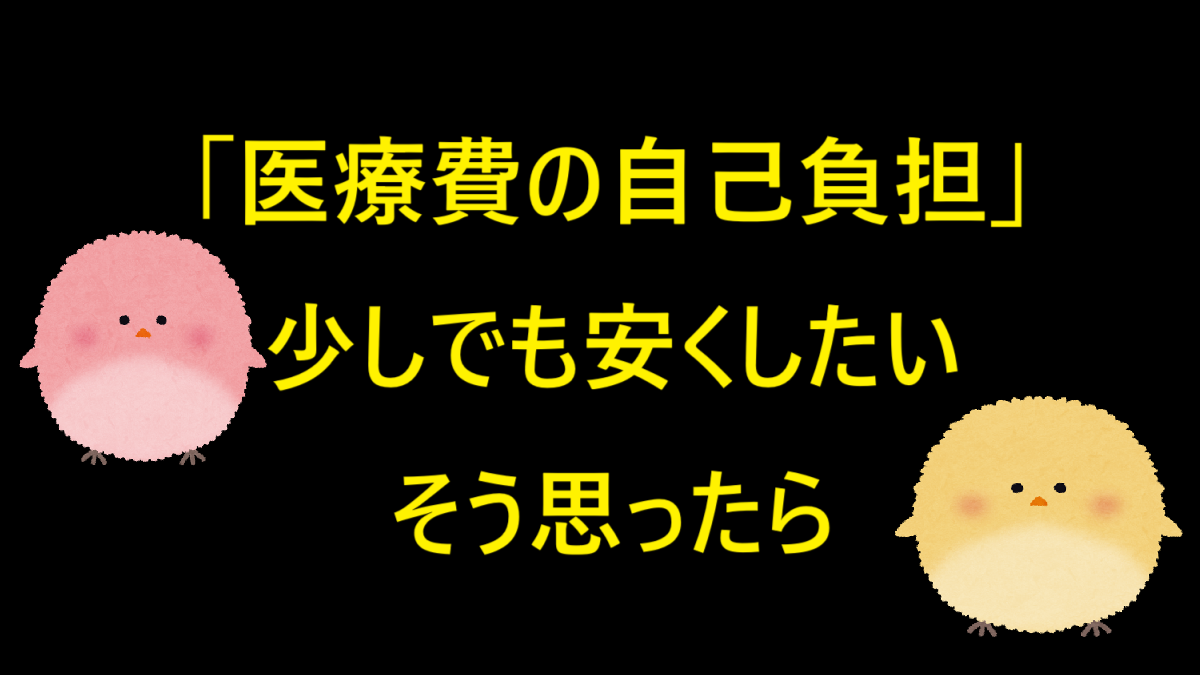





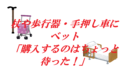
コメント